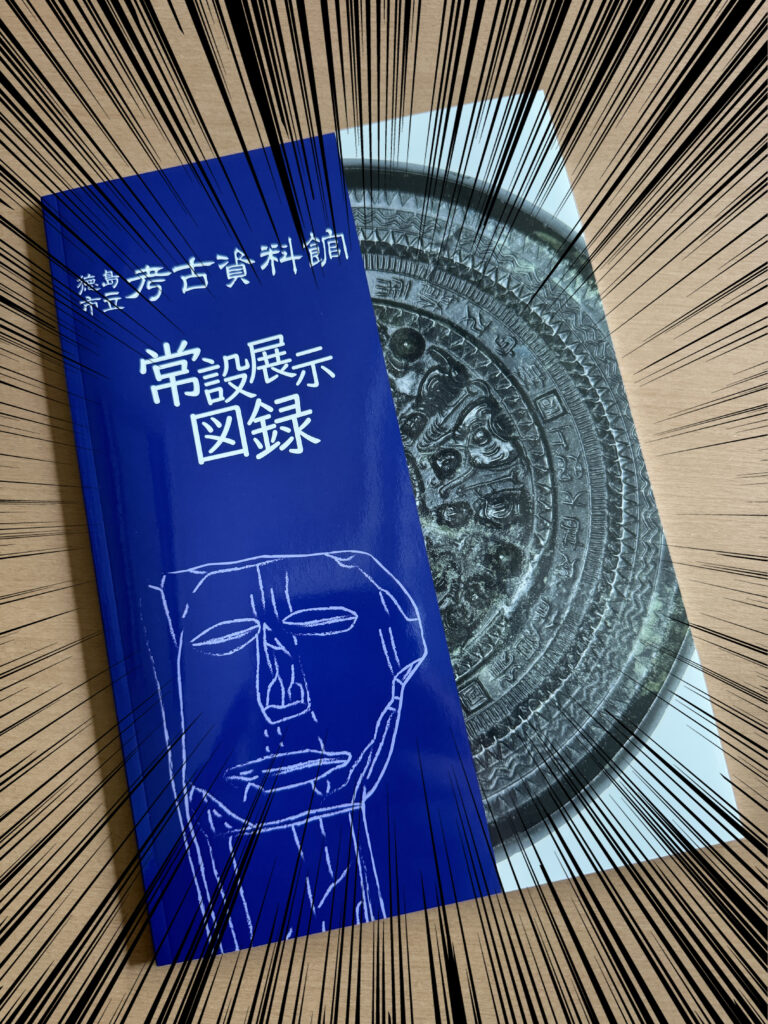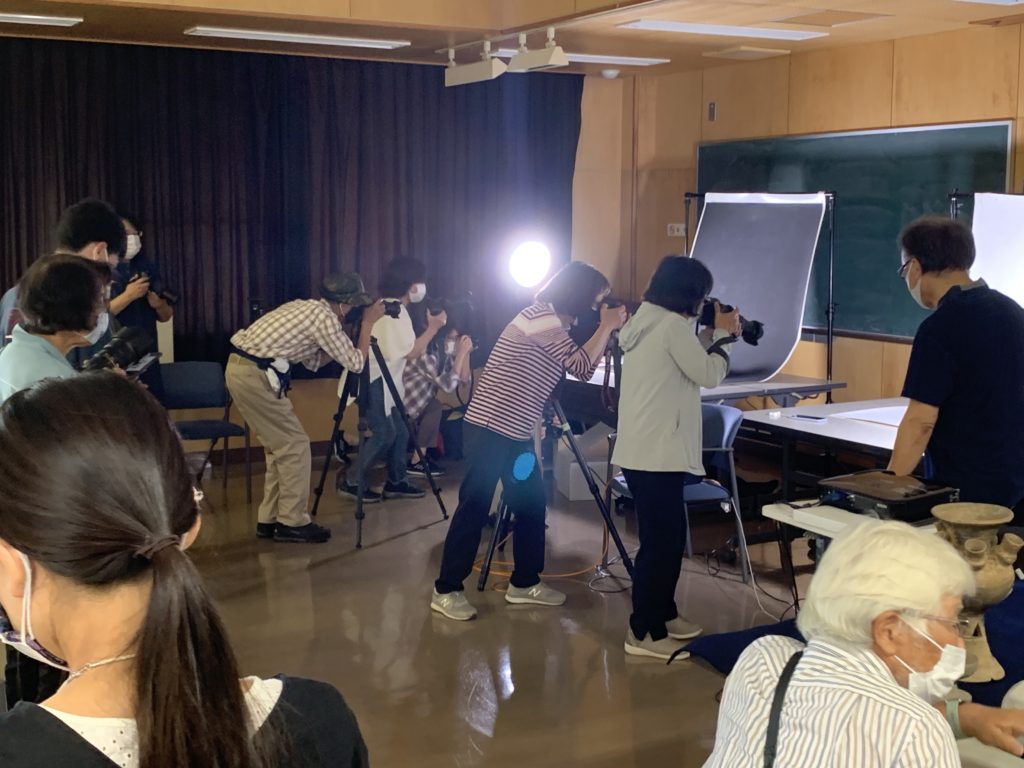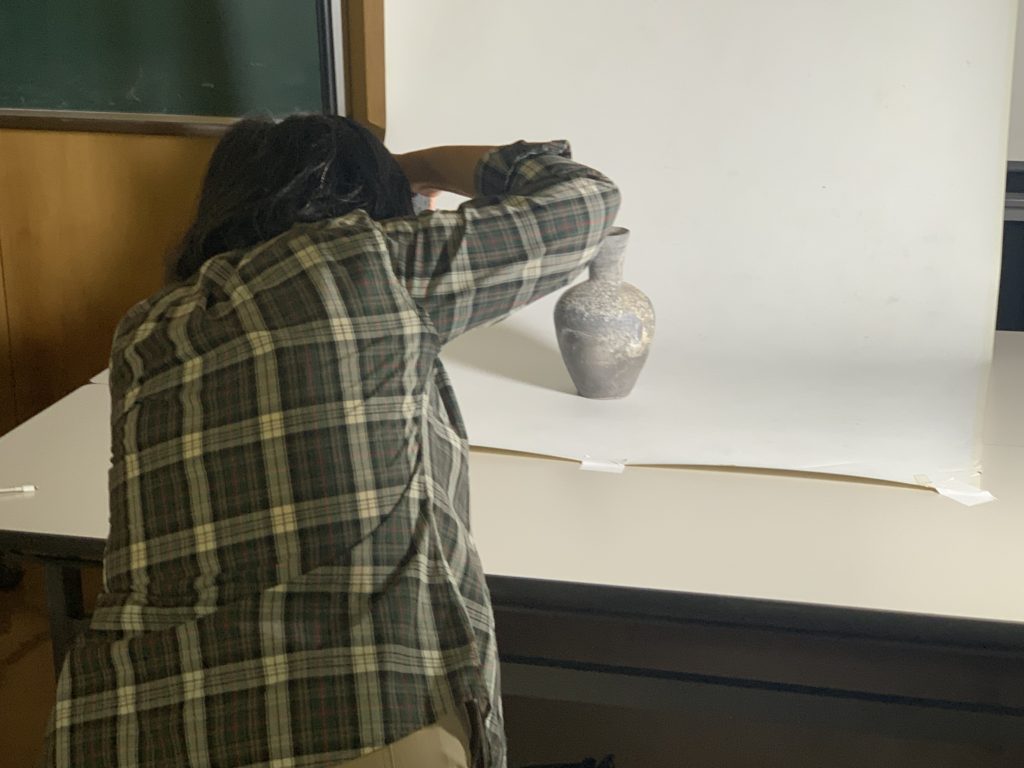考古資料館ではかれこれ5年ほど『歴史が薫る徳島市の風景写真展』を開催しています。徳島市内の歴史を感じさせる風景を写真に撮っていただき、資料館でその写真を展示するというものです。PR活動が足りなかったせいなのか、開始して以降なかなか作品の投稿が増えず加えて新型コロナの流行による外出自粛などのせいか、作品投稿数に伸び悩んでいる今日この頃です。
今年は4月に2件、5月に1件の作品が投稿があり出だし好調なのですが、6月になってすぐに投稿していただいた写真がとても面白く、勉強になったので紹介させていただきます。

今こそ欲しい鉄道 P.N.美ヶ さん
応神町の古川という場所にかつて鉄道の駅があったとのことでそのあたりの現在の風景を写していただいたものです。作品の投稿本当にありがとうございます。
古川まで鉄道が通っていたことを私も初めて知り驚いたのですが、調べてみると戦前に阿波電気軌道(のちに阿波鉄道)という鉄道会社が存在し、鉄道が運営されていたそうです。現在のJR四国の鳴門線や廃線になった鍛治屋橋線は阿波電気軌道の路線で、のちに国有化されて国鉄の路線になりJR四国に引き継がれたという経緯があるそうです。
グーグルマップを見るとわかりますが、吉成駅から佐古駅に続く線路に対して左右対称に開くように道路がありますが、これが古川まで続いていた線路の名残のようですね。吉成駅から古川駅の間には中原駅があり、この駅からは徳島の中心地まで連絡船が通っていたそうです。
残念ながらこの路線については国有化されることなく戦前に廃線となってしまいました。ちなみに阿波電気軌道という名称ながら電車は一度も走ったことが無く廃線まで蒸気機関車が走っていたそうです。
古川駅があった場所にそれを伝えるような名残りは何も無いようで、投稿していただいた美ヶさんも古い地図と駅の近くにあるお寺を目印に駅の場所を探されたそうです。
お寺を目印にしてフィールドワークをするのは歴史地理学では正しいやり方なんですよ。意外かもしれませんが神社は社名はそのままに結構場所を変えたりします。これを遷座といいますが戦災にあったり災害にあったりすると「縁起が悪い」ということで移転するんですね。他には氏子の転居にあたって神様だけ置いていくのは偲び無いということで、一緒に引っ越してしまうケースもあります。それに対してお寺はあまり場所を変えません。その理由を記し始めると長くなってしまうので割愛しますが、お寺が移転しないというよりも神社は移転しやすいので神社を目印にするよりもお寺を目印にした方が間違いが少ないと言われています。
作品のタイトルにもあるように路線が今でも残っていたらどんな感じだったんでしょうね。少なくとも古川駅があった場所のそばに建つ四国大学の学生さんは通学が楽だっただろうなぁ。吉野川を横断して徳島市街地へぬける水上交通も観光の名所になったかもなぁと想像してしまいます。そんなことを思いながら歴史散歩がしたくなる作品を送っていただき本当にありがとうございます。
考古資料館では引き続き『歴史が薫る徳島市の風景写真展』への作品投稿をお待ちしています。投稿していただいた写真は随時考古資料館のラウンジにて掲示していますので、ぜひご覧ください。折に触れてこのブログでも紹介していきたいと思います。
詳しくは下記のURLをクリックしてください。
http://www.tokushima-kouko.jp/rekishi_photo.html